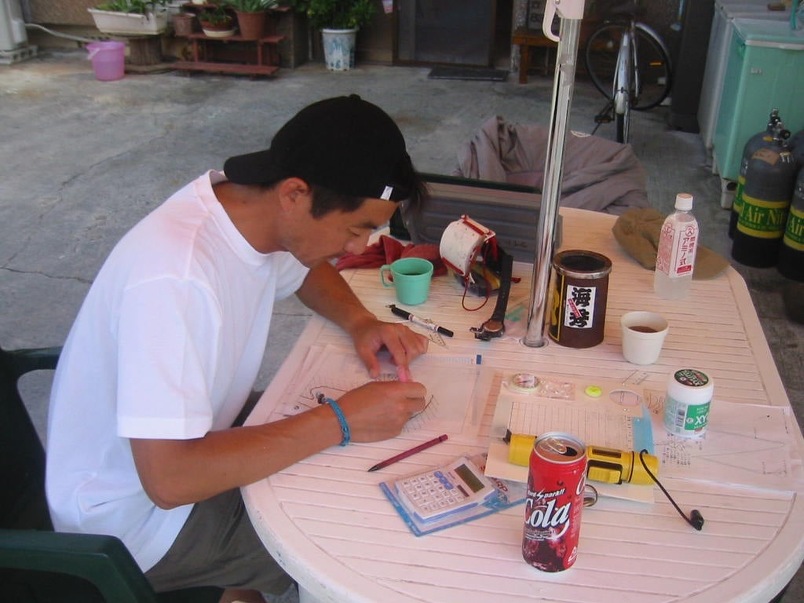沖縄・久米島の海の底には「ヒデンチガマ」と呼ばれる大きな洞窟があります。
そこはダイバーにとってまさに“未知の世界”。いまから20年以上前に長年にわたり、冒険心あふれるTDIケイブダイバーたちが調査を続けていました。
その中でも長期に渡って活動してきたのが、TDIインストラクタートレーナーの 鷹野 与志弥さん。
今回は、当時の探検の思い出や、そこから得た学びを伺います。
Q1. 初めて潜ったときの気持ち
── ヒデンチガマに初めて潜られたとき、どんな印象を受けましたか?
鷹野さん:
「ヒデンチガマ」が発見されたのは、ちょうどテクニカルダイビングという新しい潜水分野が日本に入ってきた頃でした。TDIをアメリカから日本に導入した幹部からは「テクニカルの原点はケーブにある」と繰り返し聞かされていましたが、当時の日本には一般に潜れる本格的な水中洞窟はほとんど存在しませんでした。そうした中で久米島に「ヒデンチガマ」が発見されたのです。
偶然にも発見者がTDI-JAPANの幹部と知り合いだったことから、TDI-JAPANが調査に乗り出すことになり、私も幹部に強く勧められて調査メンバーとして現地に向かいました。もっとも、当時の私は本格的な洞窟潜水の経験がなく、深海や沈船には関心があったものの、洞窟については「ただの暗い穴にすぎないのでは」という先入観があり、正直あまり興味を持っていませんでした。
しかし、久米島に到着すると、すでに集まっていたダイバーたちの「ヒデンチガマ」にかける強い情熱が伝わってきました。私はまずケーブダイビングに必要な最低限の知識とスキルを訓練し、翌日、いよいよ初めて「ヒデンチガマ」に潜ることになりました。
水深約35mにある小さな穴を目にした瞬間、突然に胸が高鳴りました。外見は何の変哲もない小さな穴ですが、その奥に未知の空間が広がっていると想像しただけで、心が震えたのです。先行するダイバーに続いて体をかすめながら進むと、洞窟はやがて大きく広がり、ライトに照らされた先には奥深く続く世界が現れました。
光の届かない、水に満たされた静謐な世界。時間が止まったかのような感覚は、それまでの潜水では経験したことのないものでした。私は無意識にさらに奥へ進もうとしたのですが、正式なケーブトレーニングを受けていなかったため、グループリーダーから「帰る」のサインが出されました。
出口方向に目を向けると、青く輝く光が差し込み、それはまるで暗黒の宇宙に浮かぶ地球のように見えました。生の世界への入口に戻る感覚を覚えたのです。
滞在時間はわずか5分ほどに過ぎませんでした。しかし、その短い体験は強烈に心に残り、半年後にはフロリダで本格的なケーブ訓練を受ける決意を固め、単身フロリダへ向かうことになりました。
Q2. なぜ調査を続けたのか
── 危険もある場所で、長年にわたり調査を続けようと思ったのはなぜですか?
鷹野さん:
私が担当していたのは「測量」でした。ヒデンチガマを「おおよそこのような形」と感覚的に語るのではなく、測量データに基づいて正確な地図や模型を作成することに意義を感じていました。これにより、潜ったことのない人にも洞窟の姿を具体的に理解してもらうことができるからです。
さらに、洞窟内では「クメジマドウクツガザミ」のような親族新種の発見もありました。どの地点で何が発見されたかを地図上でも記録することは、他の研究や調査にとっても大きな価値を持つと考えていました。
Q3. 洞窟の魅力と大変さ
── ヒデンチガマの中で「ここはすごい!」と思った景色や瞬間はありましたか?逆に「これは大変だった」という出来事も教えてください。
鷹野さん:
入り口から約90m進んだ先に、私たちが「大ホール」と呼んでいた場所があります。そこは特に広大な空間で、立派な「つらら石」や「石筍」といった二次生成物を観察することができます。これらはおそらく約2万年前、氷河期に海面が低く陸上にあった時代に形成されたものと考えられます。その後、光の届かない世界となった場所に再び光を差し込み、目の前でその姿を確認できる瞬間は、水中洞窟ならではの大きな魅力だと感じます。
一方で、当然ながらリスクも伴います。ヒデンチガマは水深が深いためガスの消費量が多く、減圧症のリスクも高まります。さらに海洋洞窟であるため、風や潮流の影響を受けやすく、せっかく多くの器材を運び込んでも、海峡が荒れ一度も潜れずに帰らざるを得ないことも少なくありませんでした。
Q4. 仲間との絆
── 探検を一緒にした仲間との思い出で、特に心に残っているエピソードはありますか?
鷹野さん:
私にとって洞窟潜水のようにリスクの高いダイビングでは、仲間との信頼関係と思いやりが最も重要です。恐怖や不安を感じた時、「やめたい」と思った時、「何かおかしい」と思った時に、率直に伝えられる雰囲気がなければなりません。そうした信頼関係が、安全を守るうえで私には欠かせないのです。
ヒデンチガマが発見された当初はメディアにも取り上げられ、日本各地から多くのダイバーが調査に参加しました。しかし人が増えるほど、それぞれの思惑や意見の相違から時には口論している人達や、自分の意思を押し通すダイバーもいました。
ところが3年も経つと世間の関心は薄れ、最終的に測量調査を続けていたのは私ともう1人の二人だけになりました。結果的に意見が合いやすく、互いにプレッシャーを感じることもなく、自分たちのペースで調査を進めることができました。ヒデンチガマが注目されなくなったことは、私たちにとってはむしろ幸運だったのかもしれません。
Q5. 探検から学んだこと
── ヒデンチガマでの経験は、ご自身にどんな学びや気づきを与えてくれましたか?
鷹野さん:
ヒデンチガマの地図や模型づくりに夢中になるあまり、周囲のことに目が向かなくなっていた自分がいました。
地図や模型が完成したとき、展示会で発表できたとき、それぞれに大きな達成感や喜びがありました。しかし同時に、その過程で見落としたものや失ったものもあったと感じています。
振り返ることで、成果だけでなく、自分の姿勢や在り方を見直すきっかけになりました。
Q6. 次の世代へ伝えたいこと
── これからダイビングを始める人や、探検に憧れる若いダイバーへ伝えたいメッセージは?
鷹野さん:
水中は、地球上に存在するもう一つの世界です。しかし呼吸ができない世界に潜るダイビングは、本質的に危険を伴うスポーツでもあります。だからこそ、自分に合った指導者を見つけ、そのもとで知識とスキルを磨き、危険を安全に変えていく努力が欠かせません。
スキルの習得には年齢や得手不得手など、個人差があります。大切なのは他者と競うことではなく、自分のスキルレベルを冷静に受け止め、その範囲に応じた潜水を行うことです。ただし、それはスキルの向上を諦めることを意味するのではありません。常に向上心を持ち続けることも重要です。
「探検」と一言でいっても、求めるものや評価される基準、規模や人数はさまざまです。たとえ誰からも注目されず、誰にも理解されなくても、それで構わないと思います。未知なるものに出会い、それに挑む情熱こそが、探検の本質だと考えます。
終わりに
ヒデンチガマは、TDI JAPANにとって、ただの洞窟ではなく「挑戦と発見の舞台」でした。
鷹野さんの言葉からは、冒険心を持ちながらも仲間と共に安全を大切にし続けた姿勢が伝わってきます。
私たちSDI/TDIは、こうした挑戦の歴史を大切にしながら、次の世代に安全で魅力的なダイビングを届けていきます。
https://www.sditdierdi.jp/blog/entry-358.html
インストラクター紹介 インストラクターNo.: #5262 インストラクター名 : 鷹野 与志弥 YOSHIYA TAKANO ファシリティ紹介 ファシリティ名:ASDI ファシリティHP: https://asdi.info/ 自己...
アスディ | 関東 | ファシリティ | SDI / TDI / ERDI / PFI /First Response 日本サイト- ダイビング教育機関/指導団体・Cカード
https://www.sditdierdi.jp/facility/kanto/asdi.html
ファシリティ紹介 千葉県野田市に在籍するファシリティ。 レジャー(スポーツ、テクニカル)活動、特殊潜水(作業、救助)活動まで、主にプロフェッショナルへの指導を行います。 消防隊員、...
新着記事
-
「誰かが守る安全」から“みんなで守れる安全”へ。"2026 SDIJAPAN チームセーフティプロジェクト始動"
2026/12/31

-
【パーティ】2026年4/5(日) ONE DIVE FAMILY PARTY IN TOKYO 参加予約開始!(先着50名プレゼント付)
2026/04/05

-
【名古屋展示会】2026年3/13-14(金土)ダイビングメッセ2026in名古屋開催のお知らせ
2026/03/14

-
【エモンズシリーズ 第3弾】なぜエモンズなのか
2026/02/13

-
【募集!】第4回 稲積水中鍾乳洞プロジェクト 参加者募集!|申込フォームはこちら
2026/01/25

-
コンピュータ・ナイトロックスeラーニング日本語リリース
2026/01/17

コースで絞り込む
キーワードで絞り込む
タグで絞り込む
- #ERDI
- #PFI
- #SDI
- #sdi-sn
- #SDIコースディレクターコース
- #TDI
- #tdi-nx
- #ういてまて
- #インストラクターアップデート
- #エイジングダイバー
- #エモンズシリーズ
- #オンライン
- #カバーンダイビング
- #ケーブダイビング
- #サイドマウント
- #シニアダイバー
- #スノーケラー
- #セノーテ
- #セミナー
- #ソロダイバーコース
- #ダイビングの始め方
- #チューク
- #ディープダイビング
- #トレジャーズ
- #ファーストレスポンストレーニングインターナショナル
- #ブルーオーシャンフェス
- #プラヤデルカルメン
- #ボランティアダイバーズ
- #ミクロネシア
- #レックダイビング
- #安全対策
- #展示会
- #潜水事故
- #着衣泳
- #稲積水中鍾乳洞プロジェクト